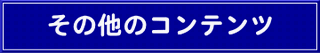其乃五 特定の分野に於いて華々しい業績を残したハンターには星が一つ与えられる
○本条は、ハンターの称号(
一ッ星への昇任)について述べているものである。
○一ッ星への昇任基準(=「華々しい業績」の定義)や、決定に至る過程等は不明である。
会長の権限が絶大である協会においては、会長の独断で星の授与を決定することも過去にはあったのかもしれない。
現在シングルであることが判明しているのは
メンチ、ツェズゲラ、イックションペ、
モラウ、サンビカ、ブシドラ、キューティーの7名であるが、メンチやツェズゲラの紹介頁をみると、それぞれ生業としているハンターの中では指折りの実力者であるということがみてとれる。
▼筆致の改正案
(一ッ星への昇任)
第5条 特定の分野において、華々しい業績を残したと認められるハンターには、称号として星が一つ与えられる。
其乃六 五条を満たし且つ上官職に就き 育成に携わった後輩のハンターが星を取得した時 その先輩ハンターには星が二つ与えられる
○本条は、ハンターの称号(
二ッ星への昇任)について述べているものである。
○ハンター十ヶ条の筆致については、読者にわかりやすいように記したものと思われるが、ここは正確を期すため、表記されていない「五条」という言葉使いではなく、「前条」とするのが望ましい。
同様に「星が二つ」では、「
其乃五で星1つ授与」+「
其乃六で星2つ授与」=「星3つ授与」となってしまうため、「星が二つ」ではなく「さらに星が一つ」、もしくは「二つ目の星が」と記すべきである。
○「上官職」というものの定義が不明であるが、ビスケ→
ウイング、ウイング→ゴン・キルア・
ズシ、
イズナビ→クラピカ、モラウ→
ナックル・
シュート、
ノヴ→
パームなどの関係がヒントとなる。
格闘や念の習得について、指導する師匠と弟子の関係を指している又は近いのではないかと考えられる。
○シングルになり得るハンターは、その経験や修得した技術により、他ハンターの指導的立場となることが予想される。
自らの技術を他のハンター伝授、継承することで初めて次のステップ(ダブル)に行けるというシステムは、とかく個人事業主になりがちなハンター達の結束も促すことになり、組織としても望ましい形態であるといえる。
▼筆致の改正案
(二ッ星への昇任)
第6条 前条を満たし、かつ上官職に就き、育成に携わったハンターが星を取得したとき、その上官職となったハンターには、称号としてさらに星が一つ与えられる。
其乃七 六条を満たし且つ複数の分野に於いて華々しい業績を残したハンターには星が三つ与えられる
○本条は、ハンターの称号(
三ッ星への昇任)について述べているものである。
○モラウについては、シングルから一気にトリプルへ昇任する噂もあるが、実際に二ッ星を飛び越しての昇任も可能である。
ナックル、シュートが
キメラアント駆逐への貢献を理由にシングルの称号を得た場合、2人の師匠であるモラウはダブルへ昇任、加えて自らのキメラアント駆逐への貢献度が評価され、「シングルで得た分野以外の業績」を理由にトリプルへ昇任するというシナリオである。
○なお、弟子であるハンターがシングルになると、師匠であるハンターも自動的にダブルに昇任するわけではない。
弟子がシングルに昇格時、師匠が星なしであるケースや、師匠が既にダブルかトリプルであるケースなどがこれにあたる。
また、初めから念を修得しているヒソカやイルミについては、師匠にあたる人物がいないため、ケース自体が発生しないと考えられる。
○「
其乃六」と同様、「星が三つ」ではなく、「さらに星が一つ」、もしくは「三つ目の星が」とすべきである。
文面どおりだと、其の五で星1つ、其の六で星がプラス2(=星3)、本条で星がプラス3(=星6)と読み取れてしまうからである。
▼筆致の改正案
(三ッ星への昇任)
第7条 前条を満たし、かつ複数の分野において、華々しい業績を残したと認められるハンターには、称号としてさらに星が一つ与えられる。
其乃八 ハンターの最高責任者たる者 最低限の信任がなければその資格を有することは出来ない
最低限とは全同胞の過半数である
会長の座が空席となった時 即ちに次期会長の選出を行い 決定するまでの会長代行権は副たる者に与えられる
○本条は、ハンターを統べる「長の選出」について述べているものである。
○会長不在の際は、副会長がその職務を代行する。次期会長の選出を行うまでは、副会長の専決が可能ではあるが、「即ちに次期会長の選挙を行い」という文面が、協会の方針決定や事業執行に関する独占行為を阻んでいる。
この場合の「即ちに」とは、選挙を始めるにあたり必要となってくる常識的な時間の範囲は含まない。
「常識的な時間の範囲」とは、例えば選挙に必要な人員の招集、配置、ルールの決定、会員への告知などが該当する。
したがって、副会長が会長権限をできるだけ長く手にしたいがために、常識的は時間の範囲を超えて、選挙の開始を延期するようなことはできない。
○一方で、会長選挙を始められない相当の理由があれば、選挙の開始を遅らせることはできる。
例えば東日本大震災のときがそうであったように、天変地異などにより物理的に動きがとれない場合や、副会長や参謀まで含めて事故がある場合などによるものである。
これらは、天変地異からの回復(インフラ復旧など社会的な現状復帰)や、新たな代行者の決定など、延期となる原因が解消した時点から「即ちに」選挙が開始されることになる。
○ただし、
第13代会長選挙時のように、ルールを決め、選挙を開始した後で、なかなか会長が決まらないことは遅延行為ではなく、単なる結果といえる。
第13代会長選挙の際、
パリストンはなかなか決着がつかないように選挙を運んだ節があるが、道義的な問題はともかく、十ヶ条上は問題ない。
○パリストンの台詞にもあるように、副会長が独裁体制を築く根拠として、本条を用いることは間違っていない。
しかし、そのような行為が他のハンター達の信任や、社会的な信用を得られるかは疑問である。
▼筆致の改正案
(長の選出)
第8条 ハンター協会(以下「協会」という。)の最高責任者(以下「会長」という。)は、最低限の信任がなければその資格を有することはできない。
2 前項における最低限の信任とは、ハンターの過半数の信任をいう。
3 会長の職が空席となった場合は、ただちに会長の選出を行う。会長を決定するまでの会長代行権は、副会長職の者に与えられる。
其乃九 新たに加入する同胞を選抜する方法の決定権は会長にある
但し従来の方法を大幅に変更する場合は全同胞の過半数以上の信任が必要である
○本条は、「新規会員の決定」について述べているものである。
○本条の権限はかなり大きなものであり、会長になる一番のメリットやその動機と考えることもできる。
審査部を抱き込んだと言われたパリストンが会長職に就くことを
十二支んから警戒されたのは、本条によりパリストンの意向に沿った者のみを採用し、一大派閥を作り上げ協会を私物化するという思惑がみえたからだと思われる。
○
テラデインは本条の改正を唱えていた。
ブシドラが、
其乃四を改正することで未然に凶悪犯罪を防ごうとした一方、テラデインは本条に手を加えることによって、犯罪を起こしそうな輩は試験の段階で排除するという主張をしている。
武闘派のブシドラと、非武闘派のテラデイン、双方の考え方の違いが表れており興味深い。
普通に考えれば、テラデインの主張が最も常識的と思える一方で、本条により犯罪歴のある者もハンターとして認定されている実態にあることから、ハンター協会は、社会悪を取り締まる警察機関的な位置付け・役割ではないことを表しているといえる。
○「大幅に変更」の度合いの解釈が難しいところではあるが、現状は「協会は会員となっているハンターに試験官への就任を委任する」「協会から委任されたハンターが、試験官としてその試験の内容を決定できる」という極めて試験官の自由度が高い設定であるため、何を変えても「大幅な変更」という枠に入ってくるように思われる。
○なお、「過半数以上」という表記であるが、「以上」という筆致は必要ない。
「過半数」とは、全体の数の半分を超える数を指す一方、「以上」とは、ある基準を含めそれより大きい(多い)ことを指す。
ある事項を決定するため、100人のハンターがいた場合、半数である50人の賛成で可決するのであれば「半数」又は「半数以上」、100人の半分を超える人数である51人の賛成で可決するのであれば「過半数」という筆致になる。
ただし、賛否が同数となり、組織の意思決定ができなくなる事態を避けるため、法律から町内会の規約に至るまで、意思決定は「過半数(の賛成)」としている筆致が圧倒的に多い。
▼筆致の改正案
(新規会員の決定)
第9条 協会へ新たに加入するハンターを選抜する方法の決定は、会長が行う。
ただし、従来の方法を大幅に変更する場合は、ハンターの過半数の信任を得て決定する。
其乃十 此処に無い事柄の一切は会長とその副たる者 参謀諸氏とでの閣議で決定する
副たる者と参謀諸氏を選出する権利は会長が持つ
○本条は、其乃一から
其乃九までにない事例が発生した場合の「協議事項」について述べているものである。
不測の事態への対処であり、一般の契約等でもこのような筆致で確認書が交わされる。
▼筆致の改正案
(協議事項)
第10条 この条項にない事項は、会長、副会長及び協会の参謀となる者(以下「参謀」という。)で構成する閣議において決定する。
2 副会長及び参謀の選出は、会長が行う。
最終更新 2023.04.16